- 運営ブログ
【2025年】放課後等デイサービスのパンフレット作成の費用相場や無料作成方法は?
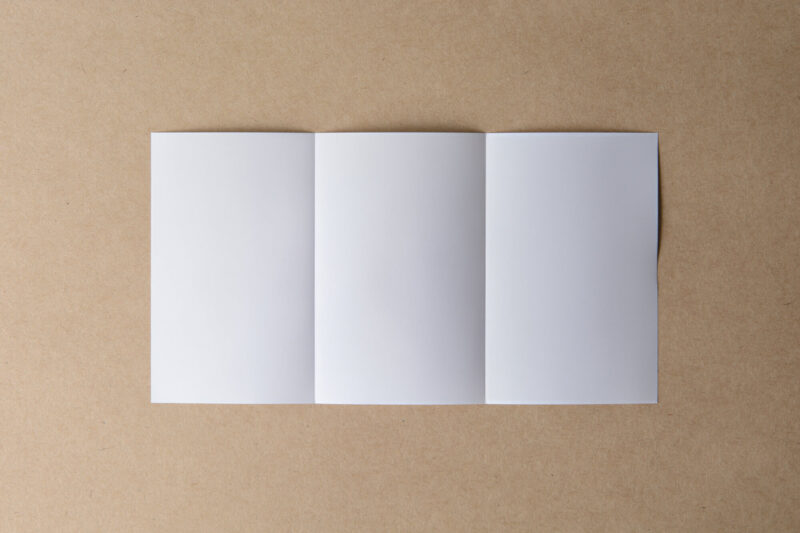
放課後等デイサービス事業所の運営において、パンフレットは単なる広告ツールではありません。利用者獲得のための重要な営業資料であり、同時に行政の実地指導でチェックされる必須書類でもあります。しかし、多くの事業所では「どのような内容を掲載すべきかわからない」「制作費用をできるだけ抑えたい」「保護者に響くパンフレットを作りたい」といった悩みを抱えているのが現実です。
本記事では、放課後等デイサービス特有のパンフレット作成ノウハウを、費用相場から無料での作成方法、法令遵守のポイントまで網羅的に解説します。開業準備中の方から既存事業所のリニューアルまで、あらゆる段階で活用できる実践的な内容となっています。
放課後等デイサービスのパンフレット基礎知識
パンフレット作成の目的と効果
放課後等デイサービスにおけるパンフレット作成の第一の目的は、事業所のことを知らない、または知りたいと思っている方に対して事業所の情報を発信・公表することです。この情報発信には明確に二つのターゲットが存在します。
一つ目のターゲットは児童の保護者です。保護者向けのパンフレットでは、支援プログラムや利用料金などの詳細情報を記載し、最終的に利用申込につなげることが目標となります。保護者の多くは複数の事業所を比較検討しているため、他事業所との差別化ポイントを明確に伝える必要があります。
二つ目のターゲットは相談支援事業所です。相談支援専門員に向けては、支援プログラムの特色だけでなく、現在の空き状況や受け入れ可能な障害特性などの実務的な情報を記載し、児童の紹介につなげることが重要です。相談支援事業所からの紹介は安定した利用者確保につながるため、継続的な関係構築を意識した内容設計が求められます。
また、パンフレットは行政の実地指導においても重要な意味を持ちます。事業所が提供するサービス内容を明確に示す資料として、運営の透明性を証明する役割を果たします。虚偽の記載や誇大表現があれば指摘の対象となるため、正確性と信頼性を重視した作成が必要です。
費用相場の詳細分析
放課後等デイサービスのパンフレット制作費用は、デザイン費用と印刷費用に大別されます。デザイン費用の相場は50,000円から200,000円となっており、この幅の大きさは依頼先の規模や経験値によって決まります。
個人事業主のデザイナーに依頼する場合、デザイン費用は100,000円以内に収まることが一般的です。個人デザイナーは固定費が少ないため、比較的リーズナブルな価格設定となっています。ただし、修正回数や対応範囲については事前に明確な取り決めが重要です。
中小規模のデザイン会社の場合、100,000円強が相場となります。企画段階からの提案力や、印刷までのトータルサポートを期待できる一方で、個人デザイナーよりも費用は高くなります。福祉業界での実績があるデザイン会社を選ぶことで、業界特有のニーズを理解した提案を受けることができます。
大手デザイン会社では200,000円以上の費用がかかることも珍しくありません。高度なブランディング戦略や市場調査を含む包括的なサービスを提供する反面、小規模事業所にとっては予算的にハードルが高い選択肢となります。
印刷費用については、1部あたり5円から30円が相場です。印刷部数、用紙の種類、折り加工の有無によって大きく変動します。一般的なA4三つ折りパンフレットの場合、100部で1,500円から3,000円、1,000部で8,000円から15,000円程度が目安となります。
掲載必須項目と法令遵守のポイント

保護者が求める情報の優先順位って?
保護者がパンフレットで最も重視するのは、支援プログラムと療育内容の具体性です。単に「個別支援を行います」「専門的な療育を提供します」といった抽象的な表現ではなく、具体的にどのような活動を通じてどのような力を伸ばすのかを明記する必要があります。例えば、「SST(ソーシャルスキルトレーニング)を通じて対人関係スキルを向上させ、集団活動では協調性と自己表現力を育成します」といった具体的な記述が求められます。
一日のスケジュールについても、平日の放課後、土曜日、長期休暇期間別に詳細を記載することが重要です。保護者は自分の生活スケジュールとの整合性を確認したいため、送迎時間、活動内容、帰宅時間を具体的な時刻とともに示す必要があります。特に働いている保護者にとって、送迎サービスの有無と対応エリアは利用可否を左右する重要な判断材料となります。
利用料金については、基本料金だけでなく、実費負担や加算項目についても透明性を持って記載することが信頼関係構築につながります。受給者証の利用方法や上限額についても簡潔に説明し、実際の負担額の目安を示すことで、保護者の不安を軽減できます。
スタッフの資格や経験については、具体的な保有資格名と実務経験年数を記載することで専門性をアピールできます。児童発達支援管理責任者、保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門資格を持つスタッフがいる場合は、その専門性を活かした支援内容も併せて紹介することが効果的です。
運営指導対応のための記載ルール
運営指導でパンフレットがチェックされる際、最も注意すべきは虚偽記載や誇大表現の排除です。「地域No.1」「100%改善」「唯一の」といった客観的根拠のない表現は、指摘の対象となる可能性があります。事実に基づいた記載を心がけ、主観的な評価は避ける必要があります。
数値データを記載する場合は、基準日、母集団、算出方法を明確にすることが重要です。例えば「利用者満足度95%」と記載する場合は、「2024年度利用者アンケート結果(回答者30名中29名が満足と回答)」といった具体的な根拠を併記する必要があります。
サービス提供体制についても、実際の運営状況と齟齬がないよう注意が必要です。パンフレットに記載したスタッフ配置や支援内容は、実地指導時に確認される可能性があるため、現実的で継続可能な内容にとどめることが重要です。
効果的なパンフレットの設計って?
理念・特徴・価値の一貫性を保つ
効果的なパンフレット作成において最も重要なのは、事業所の理念、特徴、提供価値を一本の軸で貫くことです。理念とは事業所が存在する意味であり、ミッションとも表現されます。例えば「一人ひとりの個性を尊重したサポートをする」「専門性の高い療育を提供し、地域で頼れる存在になる」といった明確な方向性を定めることから始まります。
この理念を基盤として、具体的な特徴を言語化していきます。他事業所との差別化ポイントを明確にし、なぜその特徴が重要なのかを保護者の視点から説明することが重要です。例えば、運動療育に特化している場合は、「体幹機能の向上により日常生活動作が安定し、学習への集中力向上にもつながる」といった具体的なベネフィットを示します。
価値提案においては、保護者が抱える悩みや課題に対する解決策として事業所のサービスを位置付けることが効果的です。「学校での友達関係がうまくいかない」「宿題に集中できない」「感情のコントロールが難しい」といった具体的な困りごとに対して、どのような支援でどのような改善が期待できるかを明確に示すことで、保護者の共感と信頼を獲得できます。
三つ折りパンフレットの構成は?
三つ折りパンフレットの表紙は、第一印象を決定づける最も重要な要素です。事業所名を明確に配置し、キャッチフレーズで事業所の特色を端的に表現します。キャッチフレーズは「スモールステップで『できる!』を増やす」「豊富な療育プログラムで長所が伸びる!」といった、具体的な成果をイメージできる表現が効果的です。表紙には詳細情報を詰め込みすぎず、手に取ってもらうための「入口」としての役割に徹することが重要です。
中面では、詳細情報を体系的に配置します。左側面では事業所の特色やアピールポイントを「選ばれる理由」として3つ程度に絞って記載します。中央面では具体的なサービス内容、一日のスケジュール、対象となる児童の例などを詳しく説明します。右側面では利用案内として、料金、営業時間、利用までの流れを分かりやすく整理します。情報の階層化を意識し、読み手が必要な情報を素早く見つけられるよう配慮することが重要です。
裏表紙は、具体的なアクションにつなげる導線設計が重要です。問い合わせ先、営業時間、アクセス情報を見やすく配置し、地図やQRコードを活用して連絡や来所のハードルを下げます。「まずはお気軽にご相談ください」といった親しみやすいメッセージで、問い合わせへの心理的な障壁を軽減することも効果的です。
読みやすさを向上させるには情報整理も大切
パンフレットの情報整理において、最も重要なのは情報の階層化と優先順位付けです。すべての情報を同じ重みで掲載すると、読み手にとって何が重要なのかが分からなくなります。見出しのサイズや色使い、余白の取り方によって情報の重要度を視覚的に表現し、読み手を適切に誘導することが必要です。
文章については、専門用語を多用せず、保護者にとって理解しやすい表現を心がけることが重要です。専門用語を使いすぎず、これから療育を利用するユーザー向けに分かりやすい表現を選択します。
文章量については、読みやすさとの バランスを考慮する必要があります。重要な情報は省略せずに記載する一方で、冗長な表現は避け、簡潔で分かりやすい文章を心がけます。一つの段落で一つのポイントを扱い、段落間に適切な余白を設けることで、視覚的な読みやすさも向上させることができます。
PowerPointで作成する詳細手順

事前準備と設計
PowerPointでパンフレットを作成する前に、必要な素材を整理することが重要です。事業所のロゴデータ、使用する写真、掲載する文章、連絡先情報などを事前に準備し、作業中に迷わないよう整理しておきます。写真については、利用している児童が写っている場合は保護者の許可を確認し、個人情報の取り扱いに注意が必要です。
A4三つ折りパンフレットを作成する場合、PowerPointのスライドサイズをA3サイズ(297mm × 420mm)に設定します。「デザイン」タブの「スライドのサイズ」から「ユーザー設定のスライドのサイズ」を選択し、幅42cm、高さ29.7cmに設定します。この設定により、A3用紙に印刷後、三つ折りにしてA4サイズのパンフレットが完成します。
印刷仕様の確認も重要な事前準備の一つです。利用予定の印刷会社がPowerPointファイルに対応しているか、PDF変換が必要か、トンボや塗り足しが必要かを事前に確認します。多くのネット印刷会社はOffice系ソフトに対応していますが、仕様は会社によって異なるため、事前確認が失敗を防ぐ鍵となります。
詳細作成手順
基本設定とガイドライン
PowerPointでパンフレット作成を始める際は、まずガイドラインの設定から行います。「表示」タブの「ガイド」をチェックし、三つ折りの境界線を示すガイドラインを追加します。A3サイズを3等分するため、左から14cm、28cmの位置に縦のガイドラインを配置します。これにより、折り位置を明確にし、各面のレイアウトを正確に行えます。
余白の設定も重要です。印刷時の裁ち落としを考慮し、各面の端から10mm程度の余白を設けます。重要な文字や画像は、この余白エリア内に配置することで、印刷時のズレによる切れを防ぐことができます。フォントについては、Windows標準フォントである「游ゴシック」や「メイリオ」を使用することで、印刷会社での文字化けを回避できます。
表紙の効果的な作成方法
表紙は右端の面に配置し、事業所名を最も目立つ位置に配置します。フォントサイズは24pt以上を推奨し、視認性を重視したゴシック体を選択します。事業所名の下にはサービス内容を示すサブタイトルとして「児童発達支援・放課後等デイサービス」を記載し、サービス内容を明確にします。
キャッチフレーズは事業所の特色を表現する重要な要素です。「一人ひとりの『できた!』を大切に」「遊びながら学び、学びながら成長」といった温かみのある表現で、事業所の理念を伝えます。キャッチフレーズのフォントサイズは事業所名より小さく(16-20pt程度)設定し、色使いでメリハリをつけます。
連絡先情報は表紙の下部に配置し、電話番号、住所、ホームページアドレスを記載します。QRコードを活用する場合は、ホームページや問い合わせフォームへの直接アクセスを可能にし、保護者の利便性を向上させます。QRコードは無料生成サイトで作成でき、URLが変更される可能性を考慮して定期的な確認が必要です。
中面レイアウトの設計は?
中面の左側面では、事業所の選ばれる理由やアピールポイントを3つ程度に絞って記載します。「専門スタッフによる個別支援」「豊富な療育プログラム」「安心の送迎サービス」といった具体的な特色を、それぞれ2-3行程度の説明文とともに紹介します。見出しは太字で14pt程度、説明文は10-12ptの読みやすいサイズに設定します。
中央面では、具体的なサービス内容と一日のスケジュールを詳しく説明します。平日のスケジュール例として、「15:00 お迎え・健康チェック」「15:30 おやつ・自由遊び」「16:00 個別療育プログラム」「17:00 集団活動」「17:30 帰りの準備・送迎」といった具体的な時間割を示します。土曜日や長期休暇のスケジュールも簡潔に記載し、利用者のニーズに応える情報を提供します。
右側面では、利用案内として料金、営業時間、対象者、定員などの基本情報をまとめます。料金については、「利用料金は受給者証により決定されます。詳しくはお問い合わせください」といった表現で、個別相談を促します。営業時間は曜日別に詳細を記載し、休業日や年末年始の対応も明記します。
裏表紙と事業所へのアクセス情報
裏表紙は左端の面に配置し、アクセス情報と問い合わせ先を見やすく整理します。住所は都道府県から番地まで正確に記載し、最寄り駅からの徒歩時間やバス停の情報も含めます。駐車場がある場合は台数も記載し、車での来所を検討している保護者への配慮を示します。
地図の作成には著作権の注意が必要です。GoogleマップやYahoo!マップの画像をそのまま使用することは著作権侵害となるため、簡略化した手描き風の地図を作成するか、地図作成ソフトを利用します。PowerPointの図形機能を活用して、主要な道路と目印となる建物を示した簡単な地図を作成することも可能です。
問い合わせ方法については、電話、メール、ホームページの問い合わせフォームなど、複数の選択肢を提供します。「見学随時受付中」「まずはお気軽にお電話ください」といった親しみやすいメッセージで、問い合わせへの心理的ハードルを下げることが重要です。営業時間外の対応についても記載し、メールでの問い合わせを促進します。
PowerPoint特有の技術的注意点
PowerPointでパンフレットを作成する際の最大の注意点は、印刷会社での対応可否の確認です。多くの印刷会社はPowerPointファイルに対応していますが、バージョンや設定によっては正しく印刷されない場合があります。事前に印刷会社の入稿ガイドラインを確認し、推奨される保存形式やPDF変換の設定を把握することが重要です。
PDF変換時の画質保持も重要なポイントです。PowerPointから「ファイル」→「エクスポート」→「PDF/XPSドキュメントの作成」を選択し、「最適化」で「最小サイズ(オンライン発行)」ではなく「標準(オンライン発行および印刷)」または「最高品質(印刷)」を選択します。これにより、印刷に適した画質を保持できます。
フォントの埋め込みについても注意が必要です。特殊なフォントを使用した場合、印刷会社のパソコンにそのフォントがインストールされていないと、別のフォントに置き換えられてしまいます。PDF変換時に「フォントの埋め込み」オプションを有効にするか、Windows標準フォントの使用を心がけることで、このトラブルを回避できます。
無料ツール完全活用ガイド

Canvaなら初心者でもデザインが可能
Canvaは豊富なテンプレートと直感的な操作性により、デザイン初心者でも高品質なパンフレットを作成できるツールです。放課後等デイサービス向けのパンフレット作成においては、「医療・ヘルスケア」「教育」「非営利団体」のカテゴリから適切なテンプレートを選択することが重要です。明るく親しみやすい色使いで、安心感を与えるデザインを選ぶことで、保護者に好印象を与えることができます。
テンプレートのカスタマイズにおいては、事業所のブランドカラーに合わせた色調整が効果的です。Canvaの色彩調整機能を活用し、全体的な統一感を保ちながら、事業所の個性を表現します。文字については、読みやすさを重視した日本語フォントを選択し、文字サイズと行間を適切に調整することで、視認性を向上させます。
Canvaの画像ライブラリには、児童や家族をテーマとした写真が豊富に用意されています。ただし、商用利用の場合は有料プランの契約が必要な素材もあるため、利用規約を carefully確認することが重要です。事業所独自の写真を使用する場合は、Canvaのアップロード機能を活用し、適切なサイズとトリミングを行います。
その他無料ツールの特徴比較
Adobe Expressは、プロ品質のデザインテンプレートを提供する無料ツールです。Canvaと比較して、よりデザイン性の高いテンプレートが特徴的ですが、日本語フォントの種類がやや限定的です。複雑なレイアウトや グラフィック効果を求める場合に適していますが、シンプルで読みやすいパンフレットを重視する場合は、Canvaの方が使いやすい場合があります。
ラクスルのテンプレートサービスは、印刷会社が提供するデザインテンプレートの特徴があります。最大の利点は、テンプレートで作成したデザインをそのまま印刷注文できることです。デザインと印刷を一貫して依頼できるため、ファイル形式の互換性や印刷品質の心配がありません。ただし、テンプレートの種類は他のツールと比較して限定的です。
Microsoftのテンプレートは、PowerPointやWordで利用できる公式テンプレートです。Office365のユーザーであれば、より多くの高品質テンプレートにアクセスできます。既存のOffice環境との親和性が高く、ファイルの共有や編集が容易です。ただし、デザインの自由度は専用ツールと比較してやや限定的です。
無料ツール選択の判断基準
無料ツールの選択においては、制作時間とクオリティのバランスを考慮することが重要です。短時間で一定水準のパンフレットを作成したい場合は、豊富なテンプレートを持つCanvaが適しています。一方、オリジナリティを重視し、時間をかけてでも独自性のあるデザインを作成したい場合は、PowerPointの自由度の高さが活用できます。
印刷対応の確実性も重要な判断基準です。CanvaやAdobe Expressで作成したデザインを印刷する場合、PDF形式でのダウンロードが必要となり、印刷会社での対応可否を事前確認する必要があります。一方、PowerPointで作成したファイルは多くの印刷会社で直接対応可能ですが、バージョンや設定による問題が発生する可能性もあります。
将来的な更新・修正の容易さも考慮すべきポイントです。職員の入れ替わりやサービス内容の変更に伴い、パンフレットの情報更新が必要になることは珍しくありません。PowerPointで作成したファイルは、一般的なオフィスソフトで編集できるため、外部委託なしに内部で修正可能です。一方、専用ツールで作成したデザインは、同じツールでないと編集できない場合があるため、継続的な修正コストを考慮する必要があります。
外注時の成功戦略

パンフレットのデザイン制作会社選定の基準は?
放課後等デイサービスのパンフレット制作を外注する際は、福祉業界での実績を重視することが重要です。一般的な企業パンフレットとは異なり、福祉業界特有の規制や配慮事項があるため、業界理解のあるデザイン会社を選択することで、適切な提案を受けることができます。制作会社のウェブサイトで過去の実績を確認し、児童発達支援や放課後等デイサービス関連の制作事例があるかをチェックします。
ポートフォリオの評価においては、デザインの美しさだけでなく、情報の整理方法や読みやすさにも注目することが重要です。福祉サービスのパンフレットでは、デザイン性よりも情報の伝わりやすさが重視されるため、複雑な情報を分かりやすく整理できているかを評価基準とします。また、ターゲット層に適した色使いやトーンで制作されているかも確認ポイントです。
見積もり比較時は、制作費用の内訳を詳細に確認することが重要です。企画・ディレクション費、デザイン費、修正費、データ制作費などの項目別に費用を把握し、追加費用が発生する条件についても事前に確認します。特に修正回数の制限や、印刷データ制作の対応範囲については、契約前に明確にしておくことでトラブルを回避できます。
パンフレットの発注プロセス
要件定義書の作成は、外注成功の鍵となる重要なプロセスです。パンフレットの目的、ターゲット、掲載したい情報、希望するデザインテイスト、予算、納期などを文書化し、制作会社との認識齟齬を防ぎます。
修正回数と納期の設定については、現実的で余裕のあるスケジュールを組むことが重要です。一般的にパンフレット制作では3回程度の修正を想定し、初稿提出から最終稿完成まで2-3週間程度の期間を設けます。急ぎの案件では追加費用が発生する場合があるため、できるだけ余裕を持ったスケジュールで依頼することがコスト削減につながります。
著作権と二次利用権の確認も重要な契約事項です。制作されたパンフレットのデザインデータの所有権、将来的な修正や転用の可否、使用期間の制限などを事前に確認します。多くの制作会社では、制作費に著作権譲渡費用が含まれていますが、一部では別途費用が必要な場合もあるため、契約前の確認が必要です。
制作完了後にパンフレットをどう活用する?
効果的な配布・活用方法
パンフレットの配布場所選定は、ターゲットとなる保護者や相談支援事業所が集まる場所を戦略的に選択することが重要です。小児科や発達クリニックなどの医療機関、市町村の福祉窓口、特別支援学校、療育センターなどが主要な配布先となります。配布許可を得る際は、事業所の紹介と配布目的を明確に説明し、相手機関のメリットも考慮した提案を行います。
相談支援事業所への配布においては、単純にパンフレットを渡すだけでなく、事業所の特色や空き状況を口頭で説明し、関係構築を図ることが重要です。相談支援専門員との顔の見える関係を築くことで、適切な児童の紹介につながりやすくなります。定期的な訪問によりコミュニケーションを継続し、信頼関係を深めることが長期的な利用者確保につながります。
デジタル版の活用も現代的な配布戦略として重要です。ホームページへのPDF掲載、メールでの資料送付、SNSでの紹介など、デジタルチャネルを活用することで、より広範囲への情報発信が可能になります。
まとめ
放課後等デイサービスのパンフレット作成は、単なる広告制作ではなく、利用者獲得と信頼関係構築のための重要な戦略的ツールです。保護者の視点に立った情報提供、相談支援事業所との連携強化、法令遵守への対応など、多面的な要素を考慮した設計が求められます。
制作方法については、PowerPointを活用した自作から専門業者への外注まで、事業所の予算と求めるクオリティに応じて最適な選択肢があります。重要なのは、どの方法を選択しても、事業所の理念と特色を明確に伝え、ターゲットのニーズに応える内容とすることです。
完成後の活用においては、効果的な配布戦略と継続的な改善が成功の鍵となります。定期的な効果測定とフィードバック収集により、より効果的なパンフレットへと進化させていくことが、長期的な利用者獲得と事業発展につながります。本ガイドを参考に、事業所の特色を活かした魅力的なパンフレットを作成し、地域の児童と家族により良いサービスを提供していくことを期待しています。


