- 子育てコラム
発達障害の子供の歯医者対策:障害者歯科の利用を視野に親子で乗り越えよう!
参考文献:三重県歯科医師会「発達障害を中心とした分類と特徴」

「歯医者さん行こうね」というと、泣き出したり、かんしゃくを起こしたり、あるいは頑なに拒否したりする子どもの姿に、多くの親御さんが頭を悩ませています。特に発達障害のある子どもの場合、歯科治療は一筋縄ではいかないことが多いものです。
でも大丈夫。適切な準備と理解があれば、お子さんと一緒に歯科治療の壁を乗り越えることができます。この記事では、発達障害のある子どもが歯医者さんを苦手とする理由から、家庭でできる準備、実際の診療テクニック、そして専門的な支援まで、親御さんが知っておきたい情報を徹底的に解説します。
なぜうちの子は歯医者さんが苦手なの?発達障害と歯科治療の関係
発達障害のあるお子さんが歯医者さんを苦手とする理由はさまざまですが、その多くは障害特性と歯科治療の環境が関係しています。まずはその理由を理解することから始めましょう。
感覚過敏が歯科治療を難しくしているかも
発達障害、特に自閉症スペクトラム症(ASD)のあるお子さんの多くは、感覚過敏の特性を持っています。これが歯科治療を受ける際の大きな障壁となることがあります。
キーンという音が怖い!聴覚過敏と歯医者
歯科医院には独特の音がたくさんあります。タービン(歯を削る器械)のキーンという高音、バキュームの吸引音、そして他の患者さんの声など。聴覚過敏のある子どもにとって、これらの音は私たちが感じる以上に大きく、時に痛みを伴うほど不快に感じることがあります。多くの子どもは、この「音」への恐怖から歯医者さんに行きたがらないのです。
音に敏感な子どもには、ノイズキャンセリングヘッドホンやイヤーマフを使用したり、好きな音楽を聴きながら治療を受けられるよう工夫したりすることで、ストレスを軽減できることがあります。中には治療中ずっとお気に入りの音楽を流してもらうことで、不安な気持ちが和らぐ子どももいます。歯科医院に相談してみると良いでしょう。
口の中を触られるのが苦手な理由と対処法
触覚過敏のある子どもにとって、歯科医師や歯科衛生士に口の中を触られることは、とても不快な体験です。特に口腔内は非常に敏感な部位であり、普段から歯磨きを嫌がる子どもも多いでしょう。こうした触覚過敏がある場合、少しずつ慣らしていく「脱感作」という方法が効果的です。
まずは親が優しく頬や顎、唇の周りに触れるところから始め、徐々に口の中に触れることに慣れさせていきます。例えば、毎日の歯磨き前に「今から歯ブラシでお口の中を触るよ」と声をかけながら、最初はほんの数秒だけ歯に触れるところから始めると良いでしょう。慣れてきたら少しずつ時間を延ばしていきます。歯科医院でも、いきなり治療器具を使うのではなく、まずは指で触れるなど、段階的なアプローチを相談してみるとよいでしょう。
歯磨き粉の味や感触が苦手な子どもへのアプローチ
味覚過敏のある子どもは、歯磨き粉のミント味や泡立ちを強く不快に感じることがあります。また、歯科治療で使用される薬剤やフッ素の味が苦手で、歯科治療全体に拒否感を持つケースもよくあります。家庭では、子どもが受け入れやすい味の歯磨き粉を探してみましょう。子ども用の甘い味のものや、できるだけ刺激の少ないものがおすすめです。
最近では、様々な味や香りの歯磨き粉が販売されているので、お子さんと一緒に選んでみるのも良いでしょう。例えば、いちご味やぶどう味など、子どもが好きな味の歯磨き粉を使うことで、歯磨きへの抵抗感が減ることがあります。歯科医院では事前に味覚過敏について伝え、可能な限り刺激の少ない材料を使用してもらうようお願いするとよいでしょう。
発達障害の子供が歯医者さんとうまくコミュニケーションが取れない時の工夫

発達障害のある子どもは、自分の感情や痛みをうまく言葉で表現できないことがあります。また、医師からの説明を理解するのも難しいことがあります。これらのコミュニケーションの壁が、歯科治療への不安や恐怖を増幅させることがあります。
痛みを伝えるための親子だけのサイン作り
言葉でうまく表現できない子どもでも、シンプルなサインなら使えることがあります。例えば、「痛いときは手を挙げる」「不安なときは親の手を握る」といった、治療中でも使えるサインを事前に決めておくと良いでしょう。歯科医師にもこのサインについて事前に伝えておくと、治療中に子どもの意思を尊重してもらいやすくなります。
うちの子の場合は、痛みを感じたら人差し指を1本立てる、怖くて休憩が欲しい時は2本立てる、というシンプルなサインを決めました。歯科医師や衛生士にも伝えておくことで、お互いの理解が深まり、子どもも「自分の気持ちが伝わる」という安心感を持ち、治療への不安が軽減されることがあります。
歯医者さんの説明をもっと分かりやすくする方法
発達障害のある子どもの中には、言葉による説明だけでは状況を理解しにくい子もいます。そんな時は視覚的な補助を活用しましょう。絵カードや写真を使って治療の流れを説明したり、実際に使う器具をあらかじめ見せて触らせたりすることで、「何が起こるのか」をより具体的に理解できるようになります。
例えば、「まず歯を見て→次に歯を磨いて→最後にフッ素を塗る」という流れを示した絵カードを用意しておくと、子どもは治療の見通しを立てやすくなります。また、簡潔で具体的な言葉を使い、一度に伝える情報量を少なくすることも重要です。「これからお口の中を見せてね」「3つ数えたら終わるよ」など、短く明確な指示が理解しやすいでしょう。
何が起こるか分からない不安を減らすヒント
発達障害のある子どもにとって、予測できない状況は大きな不安や恐怖の原因となります。特に初めての歯科受診では、「何をされるのか分からない」という不安が強く、パニックになりやすいものです。
初めての歯医者さんで感じるドキドキを和らげるコツ
初めての歯科受診前には、歯医者さんがどんな場所かをあらかじめ知る機会を作りましょう。歯医者さんを題材にした絵本を読んだり、歯科医院のホームページで診療室の写真を見たりするのも良い方法です。可能であれば、実際に通う予定の歯科医院に事前見学に行くのが最も効果的です。
多くの歯科医院では、治療前の見学や慣らし訪問を歓迎してくれます。実際の環境を見ることで、「ここはどんな場所なのか」「誰がいるのか」「どんな音がするのか」がわかり、子どもの不安は大きく軽減されます。見学時に歯科医師や衛生士と少し会話をすることで、人に対する警戒心も和らぐことがあります。
これから何をするの?発達障害の子供に見通しを立てる具体的な方法
発達障害のある子どもにとって、先の見通しが立つことは安心感につながります。歯科治療においても、「いつ始まり、いつ終わるのか」「何をするのか」といった見通しを立てることが重要です。タイマーを使って「あと5分で終わるよ」と具体的な時間を示したり、治療の手順を示した絵カードを順番に見せたりすると、子どもは安心して治療を受けられるようになることがあります。
また、「歯を3本見たら終わり」など、具体的な終了条件を示すのも効果的です。私の子どもの場合、「ライトを当てて→ミラーで見て→歯ブラシでピカピカにして→おしまい」という流れを絵カードで示すことで、とても落ち着いて治療を受けられるようになりました。終わるタイミングが分かると安心するようです。
発達特性ごとに考える:子供に合った口のケア

発達障害にはいくつかのタイプがあり、それぞれに特有の特性があります。お子さんの障害タイプに合わせたアプローチを考えることで、より効果的な口腔ケアが可能になります。
自閉症スペクトラム症(ASD)の子どもの場合
自閉症スペクトラム症のある子どもは、こだわりの強さ、感覚過敏、コミュニケーションの困難さといった特性があることも。これらの特性は口腔ケアにも大きく影響します。
こだわりの強い子の歯磨き、どうすれば続けられる?
自閉症の子どもは、日常の習慣や順序へのこだわりが強い場合があります。これを歯磨きに活かすなら、毎日同じ時間、同じ場所、同じ手順で歯磨きをすることで習慣化しやすくなります。例えば「お風呂の後に、洗面所で、いつもの歯ブラシと歯磨き粉で」というルーティンを作りましょう。
また、自閉症の子どもの中には、特定のキャラクターや色へのこだわりがある子もいます。そうした子どもには、好きなキャラクターの歯ブラシや歯磨き粉を用意すると、歯磨きへの抵抗感が減ることがあります。毎回同じ歯磨きソングを流したり、同じ言葉かけをしたりすることも、予測可能性を高め、安心感を与えることにつながります。変化を苦手とするお子さんの場合、歯ブラシを新しいものに変える時も、古いものと似たデザインを選んだり、少しずつ慣らしたりする配慮が必要かもしれません。
好きな食べ物しか食べない…そんな偏食と虫歯の関係
自閉症のある子どもには、食感や味、見た目へのこだわりから偏食がある場合が多く、特に甘いものや炭水化物に偏りがちです。こうした食習慣は虫歯リスクを高めることになります。完全に食事内容を変えるのは難しいかもしれませんが、甘いものを食べた後には必ず水で口をすすぐ習慣をつけたり、おやつの時間を決めて間食を減らしたりといった工夫が有効です。
また、フッ素配合の歯磨き粉の使用や、定期的な歯科検診でのフッ素塗布も積極的に取り入れましょう。偏食がある場合でも、噛み応えのある野菜やチーズなど、虫歯予防に役立つ食品を少しでも取り入れられると良いですね。子どもの好きな形や調理法を工夫することで、新しい食品にも徐々に慣れていくことがあります。
ADHD(注意欠如・多動症)の子どもの場合
ADHDのある子どもは、注意力の持続が難しい、じっとしていられない、衝動的に行動するといった特性があります。これらの特性は歯科治療や日々の歯磨きにも影響します。
じっとできない子どもの歯科治療、成功のポイント
ADHDのある子どもにとって、歯科治療中に長時間じっとしていることは大きなチャレンジです。そんな子どもの治療を成功させるためには、治療時間を短く区切ることが効果的です。例えば、最初は診察だけ、次は歯のクリーニングだけ、というように段階的に慣らしていくと良いでしょう。
また、治療中にストレスボールなど手で握れるものを持たせたり、好きな動画を見せたりして、少しでも落ち着いて過ごせるよう工夫することも大切です。歯科医師にも事前にADHDについて伝え、短時間で区切った治療計画を相談してみましょう。中には、治療の合間に短い休憩を入れたり、子どもが自分で「今から始めるよ」と合図を出したりする方法も効果的です。子どもに主体性を持たせることで、治療への協力が得られやすくなることがあります。
定期健診をうっかり忘れちゃう…そんな時の工夫
ADHDの特性として、予定の管理が苦手なことがあります。歯科の定期健診も「そのうち行こう」と思っているうちに忘れてしまい、結果として虫歯が進行してしまうことも。スマホのカレンダーアプリにリマインダーを設定したり、家族の予定表に大きく書き込んだりして、視覚的に分かりやすくしておくと良いでしょう。
また、多くの歯科医院では次回予約の確認メールやSMSを送ってくれるサービスもあるので、積極的に利用するのもおすすめです。家族で共有するカレンダーに予定を入れたり、冷蔵庫など目につく場所に予約票を貼っておくのも良い方法です。歯科医院によっては、予約日が近づくとリマインダーの電話をしてくれるところもありますので、受付の方に相談してみるとよいでしょう。
LD(学習障害)のある子どもの場合
LDのある子どもは、特定の学習能力に困難を抱えています。これは歯磨きの手順理解や、歯科医師の説明理解にも影響することがあると言われています。
歯磨きの手順が分かりにくい時の視覚サポート
LDのある子どもには、言葉による説明だけでなく、視覚的なサポートを取り入れると効果的です。歯磨きの手順を示した絵カードや、鏡の前に貼れるチェックリストなどを用意しましょう。例えば、「①前歯の表側 ②前歯の裏側 ③右の奥歯 ④左の奥歯 ⑤上の歯 ⑥下の歯」といった具体的な順序を示すと、子どもは自分で確認しながら歯磨きを進められます。
また、歯磨きアプリを活用するのも一つの方法です。歯磨きの時間や範囲をゲーム感覚で学べるアプリも増えています。視覚的にどこを磨いているかが分かったり、正しい磨き方をアニメーションで示してくれたりするので、理解しやすいでしょう。「どのくらいの時間磨けばいいの?」という疑問にも、砂時計やタイマーを使うことで視覚的に分かりやすく伝えることができます。このように、「見て分かる」工夫をすることで、子どもの自立した歯磨き習慣を育てることができるのです。
歯医者さんデビュー前に、発達障害の子がおうちでできる準備

発達障害のあるお子さんを歯科医院に連れて行く前に、家庭でできる準備がたくさんあります。適切な準備をすることで、初めての歯科受診もずっとスムーズになります。
子どもの心の準備、親としてできること
子どもが歯科受診に対して抱く不安や恐怖は、事前の準備で大きく軽減できます。子どもの理解度や年齢に合わせた方法で、歯医者さんについての正しい情報を伝えましょう。
絵本や動画で「歯医者さんって楽しいよ」を伝える方法
幼い子どもには、歯医者さんを題材にした絵本や動画が効果的です。「はじめてのはいしゃさん」「ノンタンはみがきはーみー」など、歯医者さんや歯磨きを楽しく描いた絵本がたくさんあります。お気に入りのキャラクターが歯医者さんに行く話なら、子どもも親しみやすいでしょう。
また、YouTubeなどには、実際の歯科医院の様子や、子ども向けに歯科治療を説明する動画もあります。これらを通じて「歯医者さんは怖いところではなく、お口の健康を守ってくれるところ」というポジティブなイメージを伝えましょう。動画を見せる際は、実際の診療環境に近いものを選ぶと良いでしょう。あまりにもファンタジー要素が強すぎると、実際の歯科医院とのギャップに戸惑うことがあります。絵本や動画を見た後は、「どんなところだった?」「何をしていたかな?」と子どもに質問して、理解度を確認するのも大切です。
ソーシャルストーリーで不安を減らす実践テクニック
ソーシャルストーリーとは、特定の状況や出来事について、視覚的にわかりやすく説明する方法です。歯科受診のためのソーシャルストーリーを作る場合、歯医者さんに行く理由から始まり、行く日時、誰と一緒に行くのか、歯医者さんでの流れ(受付、待合室、診察室、治療、終了)、歯医者さんでのルール(椅子に座る、お口を開ける、指示を聞くなど)、そして終わった後のご褒美までを含めると良いでしょう。
これらを簡単な文章と絵や写真で表現し、実際の受診前に何度か読み聞かせると効果的です。可能であれば、実際に通う歯科医院の写真を使うとより具体的なイメージが持てます。例えば「○月○日に、ママと一緒に△△歯科医院に行きます。最初に受付で名前を言います。次に待合室で待ちます。名前を呼ばれたら診察室に行きます。診察室では、大きな椅子に座ります。お医者さんがお口の中を見せてと言ったら、口を開けます…」といった具合に、具体的な一連の流れを示します。このようなストーリーを繰り返し見ることで、子どもは「何が起こるのか」を理解し、心の準備ができるのです。
うちの子に合った歯医者さん探し
発達障害のある子どもにとって、理解のある歯科医師や環境は非常に重要です。時間をかけてでも、お子さんに合った歯医者さんを探しましょう。
発達障害に詳しい歯科医院の探し方
発達障害に詳しい歯科医院を探す方法はいくつかあります。まずはインターネットで「発達障害 歯科」「障害者歯科 〇〇市」などと検索してみましょう。地域の障害者支援団体や親の会に相談するのも効果的です。同じ悩みを持つ親御さんのおすすめ情報は非常に役立ちます。療育施設や発達障害の専門医に紹介してもらうことも有効な方法です。普段お世話になっている専門家に相談すると、連携している歯科医院を紹介してもらえることがあります。
多くの地域には障害者歯科センターがあり、専門的な対応が可能です。候補が見つかったら、まずは電話で「発達障害のある子どもの診療経験があるか」「どのような配慮が可能か」などを確認しましょう。場合によっては、治療前の見学や相談だけの来院も受け付けてくれることがあります。初回は治療を行わず、環境に慣れることを目的とした訪問から始めることで、子どもの不安も軽減されます。歯科医院探しは一度で決めず、複数の候補を検討することも大切です。お子さんと相性の良い医院が見つかるまで、根気強く探してみましょう。
初回相談で必ず伝えたい「うちの子の特徴」
歯科医師にお子さんの特性をきちんと伝えることで、適切な対応が期待できます。初回相談時には、診断名と主な特性、感覚過敏の有無と種類、コミュニケーションの特徴、苦手なことや好きなこと、これまでの歯科経験、パニックになった時の兆候と対処法、服用している薬などの情報を伝えましょう。
例えば「うちの子は自閉症スペクトラム症で、特に高い音に敏感です。急な変化も苦手で、事前に説明がないと不安になります。言葉での理解は問題ありませんが、緊張すると言葉が出なくなることがあります。これまで歯科受診の経験はなく、今回が初めてです。」というように具体的に伝えると、歯科医師も対応を考えやすくなります。また、「恐竜が好きで、恐竜の話をすると落ち着きます」「パニックになりそうな時は、深呼吸を促すと落ち着きます」といった、お子さん独自の特性や対処法も共有しておくと良いでしょう。これらの情報を事前に整理しておくと、初回相談がより充実したものになります。メモを用意しておくと忘れずに伝えられるでしょう。
年齢別アプローチ法
発達障害のある子どもの歯科対応は、年齢によっても変わってきます。年齢に合わせた適切なアプローチを考えましょう。
小さい頃から始める歯医者さん慣れ(0〜5歳)
乳幼児期は歯科への恐怖心が定着する前に、ポジティブな経験を積み重ねる大切な時期です。この時期には、親の膝の上での診察が効果的です。小さな子どもは診療台に一人で座るよりも、親の膝の上で診察を受ける方が安心できます。多くの小児歯科では「ラップテクニック」と呼ばれる、親が子どもを抱きかかえる体勢での診察を取り入れています。
また、「お口の中をのぞく探検ごっこ」など、遊びの要素を取り入れると受け入れやすくなります。わずかな成功体験(例えば「椅子に座れた」「口を少し開けられた」など)でも大いに褒め、ポジティブな記憶を作りましょう。虫歯がなくても3〜6ヶ月ごとに定期検診に通い、歯医者さんが「安全な場所」という認識を育てることも大切です。小さい頃から歯科医院に慣れておくと、将来的な治療もスムーズになることが多いため、乳歯が生えてきたらできるだけ早く歯科検診デビューをすることをおすすめします。
小学生になってからの歯医者さんデビュー法
小学生になってから初めて歯科を受診する場合、既に歯科への不安や先入観を持っていることがあります。この年齢では、絵本やソーシャルストーリーなどを使い、何が起こるのかを具体的に説明することが重要です。いきなり治療ではなく、まずは歯科医院を見学するところから始め、徐々に慣らしていきましょう。
段階的なアプローチが効果的です。初回は診察室に入るだけ、次は椅子に座るだけ、その次は口を開けて歯を見せるだけ、といった具合に少しずつステップアップしていきます。また、子どもに小さな選択肢を与えることで自律感を持たせることも大切です。「どっちの歯ブラシを使う?」「どっちの味のフッ素がいい?」など、選択肢を提供することで、自分で決める機会を作ります。歯科訪問後にはちょっとした楽しみを用意しておくと、次回への動機づけになりますが、過度な報酬は避け、「歯医者さんに行けたね」という達成感を大切にしましょう。
歯科治療を成功させる小さな工夫
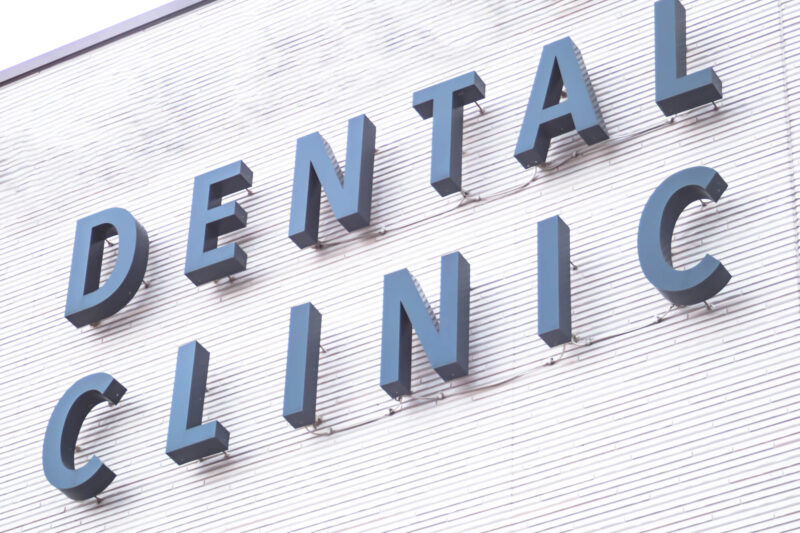
発達障害のあるお子さんの歯科治療を成功させるためには、歯科医院側の配慮と親御さんの協力が欠かせません。ここでは具体的な工夫やテクニックを紹介します。
歯医者さんにお願いしたいこと
発達障害のある子どもの治療には、歯科医院側の理解と配慮が不可欠です。遠慮せずに必要な配慮をお願いしましょう。
視覚的な手がかりで安心感アップ
発達障害のある子どもの多くは、視覚的な手がかりがあると状況理解がしやすくなります。歯科医院に「①椅子に座る→②口を開ける→③歯を見る→④歯を磨く→⑤終わり」といった治療手順をカードで示してもらうと、見通しが立って安心できます。また、タイマーの使用も効果的です。「あと3分で終わりますよ」など、残り時間が視覚的に分かるとがんばりやすくなります。
使用する前に実際の器具を見せて、触らせてもらえると「未知のもの」への恐怖が軽減されます。「ここを触りますよ」「ここをきれいにしますね」など、鏡を使って視覚的に説明してもらえると理解しやすくなります。歯科医院によっては、診療台の近くに絵カードやタイマーなどの視覚支援ツールを常備しているところもありますので、事前に確認してみると良いでしょう。診療中に使う器具を順番に並べて見せてもらうことで、「次は何をするのか」が分かり、心の準備ができます。
いつも同じ先生、同じ部屋の安心効果
発達障害のある子どもは、予測可能な環境を好む傾向があります。できるだけ同じ歯科医師や衛生士に診てもらうようにお願いしましょう。顔や声、雰囲気に慣れることで安心感が増します。また、毎回同じ診療室を使用してもらえると、環境変化によるストレスが軽減されます。
予約時間も考慮が必要です。待合室が混雑する時間帯を避け、比較的静かな時間帯に予約を入れてもらうと良いでしょう。急な治療内容の変更は混乱の原因になるため、予定変更が必要な場合は、できるだけ事前に説明してもらうようにしましょう。私の子どもの場合、最初の予約を午前中の最初の時間帯にしてもらうことで、待ち時間のストレスがなく、また子どもの集中力も高い状態で治療を受けることができました。予約時に「できれば毎回同じ先生に診てもらいたい」「静かな時間帯が良い」と伝えると、多くの歯科医院では配慮してくれるでしょう。
少しずつ慣れていく段階的な方法
発達障害のある子どもが歯科治療に慣れるには、時間をかけた段階的なアプローチが効果的です。焦らず、少しずつ前進していきましょう。
まずは見学から!歯医者さん慣れトレーニング
いきなり治療から始めるのではなく、段階的に歯医者さんに慣れていくことが重要です。まずは建物の外から「ここが歯医者さんだよ」と教えるところから始め、次のステップでは待合室に入って少し過ごし、その日は帰ります。この時、待合室のおもちゃで遊んだり、雑誌を見たりと楽しい経験を作ります。
徐々に診療室の見学、診療台に座る練習、口を開ける練習、器具に触れる体験へと進めていきます。これらのステップは、お子さんの様子を見ながら1回の訪問で複数進めることもあれば、1つのステップに何回も訪問することもあります。大切なのは「歯医者さんは安全で楽しい場所」という経験を積み重ねることです。無理に進めず、子どものペースを尊重しながら進めましょう。各ステップでの成功体験を積み重ねることで、次のステップへの不安も軽減されていきます。中には最初の数回は診療室に入るだけでパニックになる子どももいますが、何度も通ううちに徐々に慣れていくことが多いです。
少しずつ慣らしていく「脱感作」のやり方
感覚過敏がある子どもには、「脱感作」と呼ばれる方法が効果的です。これは嫌悪刺激に少しずつ慣れていく方法で、口周りへのタッチから始め、口の中への段階的接触、歯ブラシでの訓練、歯科器具への慣れへと進めていきます。
例えば、まずは頬や唇の外側など、比較的抵抗の少ない部位から触れ始めます。それに慣れてきたら、指で優しく口の中の粘膜に触れることから始め、徐々に歯に触れていきます。次に柔らかい歯ブラシで少しずつ歯に触れる練習をし、最後に実際の診察で使う器具を少しずつ導入します。まずは器具を見せるだけ、次に触れるだけ、そして実際に使用するという段階を踏みます。この方法は家庭でも実践できますが、歯科医院でのプロフェッショナルなアプローチも非常に効果的です。歯科医師と相談しながら進めると良いでしょう。毎日少しずつ行うことで、数週間から数ヶ月かけて徐々に慣れていくことが多いです。
パニックになったらどうする?
どれだけ準備をしても、歯科治療中にパニックになってしまうことはあります。そんな時のための対策も考えておきましょう。
パニックの前兆を見逃さないために
多くの場合、パニックには前兆があります。お子さん特有のパニックのサインを知っておくことで、大きなパニックに発展する前に対処できることがあります。一般的な前兆としては、体を揺すったり手をひらひらさせるなどの常同行動が増える、呼吸が荒くなる、顔の表情が硬くなるまたは極端に変わる、声の大きさや調子が変わる、目を合わせなくなるまたは特定の場所をじっと見つめる、耳をふさぐ、身体が硬直するなどがあります。
我が子の場合は、いつもより動きが多くなり、「早く終わる?」という質問を繰り返し始めたら、不安が高まっているサインです。こうしたサインに気づいたら、治療の一時中断をお願いしたり、リラックスのための休憩を取ったりすることで、パニックを予防できることがあります。歯科医師や衛生士にも子どものパニックのサインを伝えておくと、彼らも早めに気づいて対応してくれるでしょう。
パニックが起きた時のその場対処法
それでもパニックが起きてしまった場合、まずはお子さんと周囲の安全を確保します。治療器具から距離を置き、怪我のリスクを減らしましょう。可能であれば、刺激の少ない静かな場所に移動します。多くの子どもは深い圧力刺激で落ち着くことがあるため、抱きしめる、重い毛布で包むなどを試してみましょう。
お気に入りのぬいぐるみや安心グッズがあれば渡し、無理に声をかけたり落ち着かせようとしたりせず、パニックが収まるのを静かに待つことも大切です。パニックが収まっても、その日の治療を続行するかどうかは慎重に判断しましょう。無理に続けると、次回のさらなる不安につながることがあります。パニックの後は、お子さんがリラックスできる活動を提供し、次回の歯科受診に向けて再び少しずつ準備していくことが大切です。決して叱ったり、無理やり治療を続けようとしたりしないでください。子どもの感情を受け止め、「怖かったね」「大丈夫だよ」と共感することが大切です。
心強い味方!障害者歯科を知ろう

一般の歯科医院での対応が難しい場合、障害者歯科(スペシャルニーズ歯科)という選択肢があります。これらの専門機関について知っておきましょう。
障害者歯科って何が違うの?
障害者歯科は、障害のある方の歯科治療に特化した専門機関です。一般の歯科医院とは設備やスタッフの専門性などが異なります。
普通の歯医者さんと障害者歯科の違い
障害者歯科と一般歯科の主な違いは、専門的な知識と経験です。障害者歯科のスタッフは、さまざまな障害に関する専門的な知識と経験を持ち、発達障害の特性を理解し、適切な対応ができます。また、抑制具や視覚支援ツール、感覚過敏に配慮した設備など、特別なニーズに対応できる設備が整っています。
一般歯科よりも一人あたりの診療時間が長く取られていることが多く、急かされることなく、お子さんのペースで治療を進められます。歯科医師、歯科衛生士だけでなく、場合によっては心理士や言語聴覚士なども連携して対応することがあります。さらに、抑制や鎮静、全身麻酔など、さまざまな行動調整法の選択肢がありますし、お子さんの治療だけでなく、家庭での口腔ケアについての具体的なアドバイスも受けられます。障害の特性を理解した上での治療計画を立ててくれるので、一般歯科で「治療ができない」と諦めていた場合でも、可能性が広がることがあります。
近くの障害者歯科を探す方法
お住まいの地域の障害者歯科を探すには、地域の歯科医師会に問い合わせる方法があります。各地域の歯科医師会では、障害者歯科に対応している医院の情報を持っていることが多いです。また、地域の障害者支援センターに相談したり、大学病院の歯科口腔外科に問い合わせたりする方法もあります。多くの大学病院には障害者歯科部門があります。
日本障害者歯科学会のウェブサイトでは、認定医や専門医の所属する医院のリストが公開されていますので、そちらを確認するのも良いでしょう。同じ悩みを持つ親御さん同士の情報交換も大変役立ちます。親の会や療育施設で情報を得ることもできます。障害者歯科は一般歯科に比べて数が少ないため、家から遠い場合もありますが、専門的な治療を受けられることのメリットは大きいので、選択肢の一つとして検討してみましょう。実際に通院する前に電話で相談し、どのような対応が可能かを確認することをお勧めします。
障害者歯科での治療はどんな感じ?
障害者歯科での治療には、お子さんの状態に合わせたさまざまなアプローチがあります。ここでは代表的な治療方法について説明します。
行動調整法いろいろ、うちの子に合うのは?
行動調整法とは、お子さんの状態に合わせて歯科治療をスムーズに行うための方法です。テル・ショウ・ドゥ法は、治療内容をまず言葉で説明し(テル)、次に実際に見せ(ショウ)、その後に実行する(ドゥ)方法で、見通しを立てやすくなります。モデリングは、他の子どもや人形を使って治療の様子を見せることで不安を軽減する方法です。
前述した脱感作のほか、治療中に天井のテレビを見せたり好きな音楽を聴かせたりして注意をそらすディストラクション、協力的な行動をした時に褒めるなど良い行動を強化するポジティブ強化などがあります。体動が激しく安全な治療が難しい場合には、専用の抑制具を使用する物理的抑制を行うこともあります。また、鎮静剤や全身麻酔を用いる薬物的行動調整という方法もあります。どの方法が適しているかは、お子さんの年齢や障害の程度、治療の緊急性などによって異なります。歯科医師と相談しながら最適な方法を選びましょう。
鎮静や全身麻酔って必要?メリットとデメリット
通常の行動調整法では対応が難しい場合、鎮静や全身麻酔という選択肢があります。鎮静法は、意識がある程度保たれたままリラックスした状態になり、全身麻酔より身体への負担が少なく、一度に複数の治療ができるというメリットがあります。ただし、完全に動きを抑えられるわけではなく、効果には個人差があり、事前の絶食が必要なこともあるというデメリットもあります。
全身麻酔は、完全に眠った状態になるため治療中のストレスがなく、一度に多くの治療が可能で、複雑な治療も可能というメリットがあります。一方、麻酔自体のリスクがあり、事前の検査や絶食が必要で、設備のある専門機関でしか受けられず、費用が高額になることもあるというデメリットがあります。鎮静や全身麻酔は「最後の手段」ではなく、お子さんの身体的・精神的負担を減らすための選択肢の一つです。特に複数の虫歯がある場合や、緊急性の高い治療が必要な場合には積極的に検討する価値があります。治療の内容や子どもの状態によって、最適な方法は異なりますので、歯科医師としっかり相談した上で決めることが大切です。
毎日の歯磨き、こんな風に工夫してみよう
発達障害のあるお子さんの口腔ケアは日々の積み重ねが大切です。家庭での効果的な歯磨き方法を身につけましょう。
歯磨きタイムを楽しくする方法
歯磨きが苦手なお子さんでも、工夫次第で楽しい習慣にすることができます。
感覚過敏がある子どもの歯磨きテクニック
感覚過敏のあるお子さんには、柔らかい毛先の歯ブラシを選んだり、指に付けるタイプの歯ブラシから始めるなど、触覚刺激を最小限にする配慮が効果的です。歯磨き粉は泡立ちが少なく、刺激の少ないものを選び、味や香りも子どもが受け入れやすいものを探しましょう。歯ブラシを当てる圧力も重要で、強すぎず弱すぎない、ちょうど良い圧力を見つけることが大切です。
一度に全部の歯を磨くのが難しい場合は、「今日は前歯だけ」「今日は上の歯だけ」など部分的に行い、徐々に範囲を広げていくとよいでしょう。水の温度も敏感に感じる子がいるため、ぬるま湯を使うなど、快適な温度を見つけましょう。「いきなり口の中に歯ブラシを入れられるのが怖い」という子どもには、まずは自分で歯ブラシを持って、口の周りを触る練習から始め、徐々に口の中へと進めていくのも効果的です。また、歯ブラシの形や大きさ、硬さなども子どもによって好みが異なるので、いくつか試してみると良いでしょう。
歯磨きを習慣にするための楽しいアイデア
歯磨きを楽しい時間にするためには、歯磨きソングの活用がおすすめです。歯磨き中に楽しい歌を歌ったり、YouTubeなどの歯磨きソングを流したりすると、時間の目安にもなります。お気に入りキャラクターの歯ブラシを使うことで、歯磨きへの関心が高まることもあります。ぬいぐるみや人形の歯を磨いてあげるごっこ遊びから始めると、自分の歯磨きにもつながりやすくなるでしょう。
鏡で自分の歯磨きの様子を見せると、視覚的な理解が促されます。砂時計やデジタルタイマーを使って歯磨きの時間を視覚的に分かるようにしたり、歯磨きができた日にはシールを貼るチャートを作って達成感を味わえるようにしたりするのも効果的です。親が先に歯を磨く姿を見せたり、一緒に磨いたりするのもおすすめです。「お口の中に虫歯バイキンがいるから、やっつけようね」といったストーリー性のある声かけも、子どもの興味を引き出すのに役立ちます。歯磨きの習慣づけには、継続性と一貫性が大切です。毎日同じ流れで行い、少しでもできたら大いに褒めることで、子どもの自信につながります。
虫歯予防の強い味方「フッ素」活用術
フッ素は虫歯予防に非常に効果的です。発達障害のあるお子さんこそ、積極的にフッ素を取り入れましょう。
うちの子に合ったフッ素歯磨き粉の選び方
フッ素配合歯磨き粉を選ぶ際は、年齢に適したフッ素濃度のものを選びましょう。一般的に、乳幼児用は濃度が低めになっています。感覚過敏がある場合は、できるだけ刺激の少ない味や香りのものを選びます。子ども用のフルーツ味なども良いでしょう。泡立ちが苦手な子どもには、低発泡性の歯磨き粉がおすすめです。
テクスチャについても考慮が必要で、ゲル状のものよりクリーム状のもの、透明なものよりも不透明なものなど、お子さんが受け入れやすいテクスチャを探しましょう。様々な種類を試して、お子さんが最も受け入れやすいものを見つけることが大切です。また、歯磨き粉の量にも注意が必要です。特に小さなお子さんの場合は、米粒大程度の少量から始め、様子を見ながら徐々に増やしていきましょう。フッ素入り歯磨き粉を使う場合でも、磨き終わった後はしっかりとうがいをすることを教えましょう。フッ素は歯の表面に留まることで効果を発揮するので、磨いた後すぐに水で何度もうがいするのではなく、1回程度の軽いうがいにとどめると効果的です。
おうちでできるフッ素ケアのやり方
歯磨き粉以外にも、家庭でできるフッ素ケアの方法はいくつかあります。年齢によっては、フッ素洗口液でのうがいも効果的です。ただし、うがいができるようになってからの方法です。歯科医院で処方されるフッ素ジェルを歯ブラシ等につけて使用する方法もあります。自分でうがいのできない子どもには、フッ素スプレーが便利で、口腔内に直接スプレーします。
また、3〜4ヶ月に一度の歯科検診で、プロフェッショナルなフッ素塗布を受けることも重要です。フッ素ケアは継続することが大切です。お子さんの特性に合った方法を見つけ、無理なく続けられるようにしましょう。歯科医院でのフッ素塗布と家庭でのフッ素ケアを併用することで、より効果的な虫歯予防ができます。また、子どもによっては「フッ素は歯の守り神」「フッ素でお口にバリアを作ろう」といった説明が受け入れやすい場合もあります。子どもが理解しやすい言葉で説明し、フッ素ケアの意義を伝えることも大切です。
食べ方・食べ物の工夫で虫歯予防
歯磨きと並んで重要なのが、食事習慣です。発達障害のあるお子さんの食習慣にも気を配りましょう。
虫歯リスクを減らす食習慣のコツ
虫歯リスクを下げるためには、食事やおやつの時間を決め、だらだら食べ続けることを避けることが大切です。常に口の中に食べ物があると、虫歯リスクが高まります。おやつは1日1〜2回程度に制限するのが理想的です。ジュースなどの甘い飲み物は特に注意が必要で、水や麦茶など、糖分の少ない飲み物を習慣づけましょう。歯磨きが難しい場合でも、食後に水でうがいをするだけでも効果があります。年齢によっては、食後にキシリトール入りのガムやタブレットを利用するのも良い方法です。
甘いものを完全に禁止するのではなく、食べるタイミングを工夫することも大切です。おやつとして単独で食べるよりも、食事の直後に食べる方が虫歯リスクは低くなります。また、だらだら少しずつ食べるよりも、一度にまとめて食べる方が虫歯リスクは低くなります。子どもの好物が甘いものばかりの場合でも、一気に食習慣を変えようとするのではなく、少しずつ改善していくことが大切です。例えば、週に1回は甘くないおやつに挑戦する日を作るなど、無理のない範囲で工夫してみましょう。
好き嫌いが多い子どもの食事、どう工夫する?
発達障害のあるお子さんの中には、食感や味へのこだわりから偏食がある子も多いです。そんな時は栄養バランスを優先しつつ、虫歯リスクは別の方法でカバーするという考え方も大切です。噛み応えのある野菜や果物は自浄作用を高める効果があるため、お子さんが受け入れられる硬さの食材を探してみましょう。
チーズには虫歯予防効果があります。おやつや食後のデザートとしてチーズを取り入れると良いでしょう。甘いものを食べるときは、食事の直後など、まとめて食べるようにします。単独のおやつとして間食するよりも虫歯リスクが低くなります。お子さんの好きな食感や味を維持しながら、虫歯リスクの低い代替品を探してみるのも一つの方法です。例えば、砂糖の代わりにキシリトールを使った手作りおやつなどが考えられます。
食事の形態も工夫できます。例えば、同じ野菜でも、大きさや切り方、調理法を変えることで受け入れやすくなることがあります。じっくり時間をかけて、少しずつ新しい食べ物に慣れる機会を作ることも大切です。無理に食べさせようとせず、「触ってみる」「匂いをかいでみる」など、小さなステップから始めて成功体験を積み重ねていきましょう。
みんなの協力で続ける!口のケア

発達障害のあるお子さんの口腔ケアは、家族だけでなく、学校や施設など、周囲の人々との連携が重要です。
家族みんなで取り組む口腔ケア
口腔ケアは家族全員の協力があると、より効果的に継続できます。歯科医院での指導内容や、効果のあった方法などを家族全員で共有しましょう。家族用のノートを作るのも良い方法です。「朝の歯磨きはお父さん」「夜はお母さん」など、家族で役割を分担することで負担を減らします。
「歯磨きの前に使うカードはこれ」「歯磨きの順番はこうする」など、家族全員が同じ手順や言葉で接することで、お子さんも混乱せずに済みます。拒否行動やパニックが起きた時の対処法も、家族で共有しておきましょう。「今日はこうしたらうまくいった」といった成功体験も、積極的に共有します。
家族全員が口腔ケアの重要性を理解し、協力することで、お子さんも安心して取り組めるようになります。特に兄弟姉妹がいる場合は、一緒に歯磨きをする「歯磨きタイム」を設けると、良い刺激になることもあります。お子さんの成長に合わせて、徐々に自分でできることを増やしていくことも大切です。できたことをしっかり認め、褒めることで、お子さんの自信と意欲が高まります。
学校や施設と上手に連携するには
お子さんが通う学校や施設との連携も、口腔ケアを継続するための重要な要素です。お子さんの口腔ケアに関する具体的な情報(例:「苦手な味」「好きな歯ブラシ」など)を伝えましょう。家庭で使っている歯磨きの手順表や絵カードなどがあれば、それを学校でも使ってもらえるようお願いします。
給食後の歯磨きで特別な配慮が必要な場合は、具体的に相談しましょう。例えば「時間をかけて行う必要がある」「一人で静かな環境が必要」などです。学校歯科検診の際には、事前に学校歯科医に発達障害についての情報を伝え、必要な配慮をお願いしましょう。例えば、最初に見学だけする、教室で一人だけ検診を受けるなどの工夫が考えられます。
学校でうまくいったことは家庭でも取り入れ、逆に家庭でうまくいった方法は学校にも伝えるなど、情報交換を密にしましょう。学校行事や修学旅行などで宿泊を伴う場合は、事前に口腔ケアについての配慮を相談しておくことも大切です。お子さんがどのような支援があれば自分で口腔ケアができるのか、具体的に伝えておくと良いでしょう。
知っておくと助かる福祉サービス
発達障害のあるお子さんの歯科治療に関連する福祉サービスもあります。活用できるものは積極的に利用しましょう。自治体によっては、障害のある方の医療費(歯科治療を含む)の一部または全額を助成する「障害者医療費助成」制度があります。18歳未満の障害児が対象で、指定の医療機関で受けた治療の自己負担額が軽減される「自立支援医療(育成医療)」も利用可能です。
対象となる疾患がある場合は、「小児慢性特定疾病医療費助成」により医療費の一部が助成されます。全身麻酔などで高額な医療費がかかった場合には「高額療養費制度」が利用できます。これらの制度は自治体や条件によって利用できる範囲や手続きが異なりますので、お住まいの自治体の窓口や、通院している歯科医院に相談してみましょう。
また、障害者手帳をお持ちの場合は、それに応じた様々なサービスや割引が適用されることがあります。地域によっては、障害のある子どもとその家族を対象とした歯科保健教室や相談会を開催していることもありますので、地域の保健センターや福祉課に問い合わせてみると良いでしょう。必要な支援を受けながら、無理なく継続的な口腔ケアを行うことができます。
最後に
発達障害のあるお子さんの歯科治療は、確かに大変なことも多いですが、工夫と根気強さがあれば必ず道は開けます。お子さんのペースを尊重しながら、少しずつ前進していきましょう。そして何より、親御さん自身が疲れ切ってしまわないよう、時には専門家の力も借りながら、無理のないペースで取り組むことが大切です。皆さんの日々の努力が、お子さんの健やかな成長と笑顔につながりますように。


